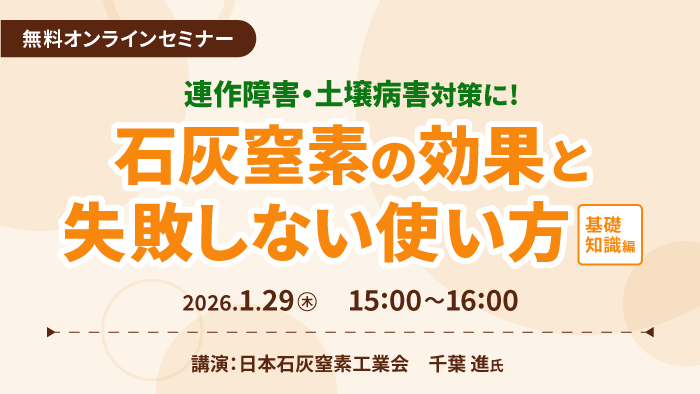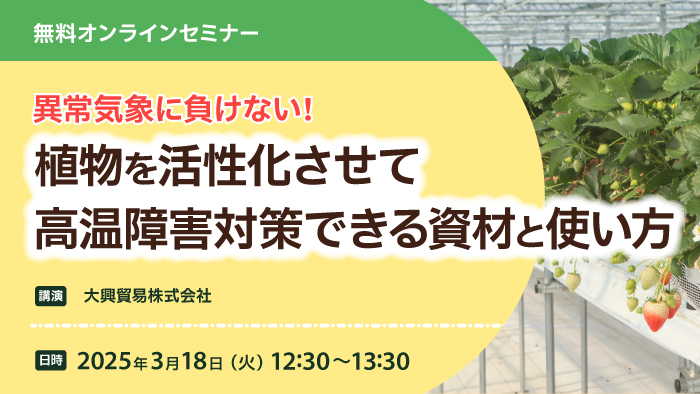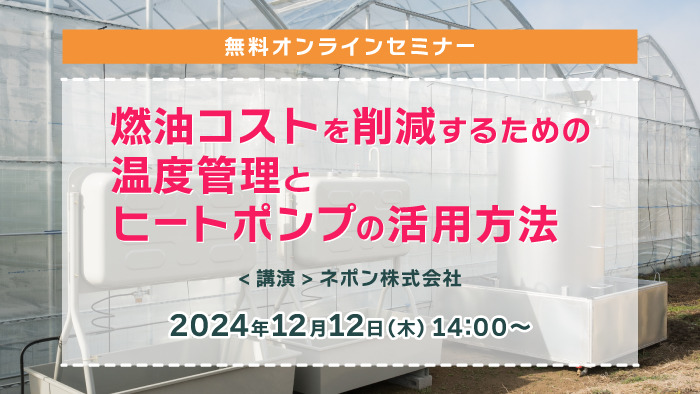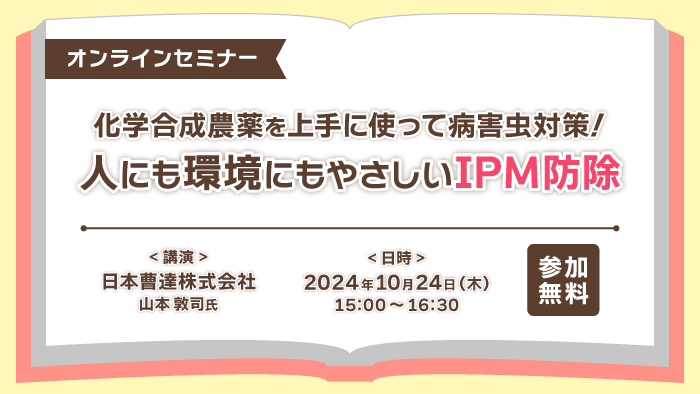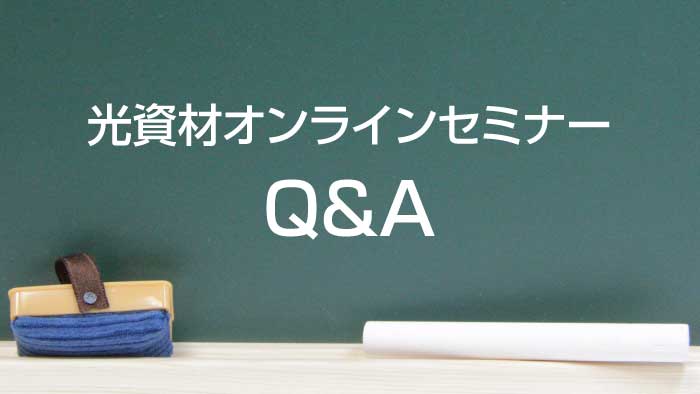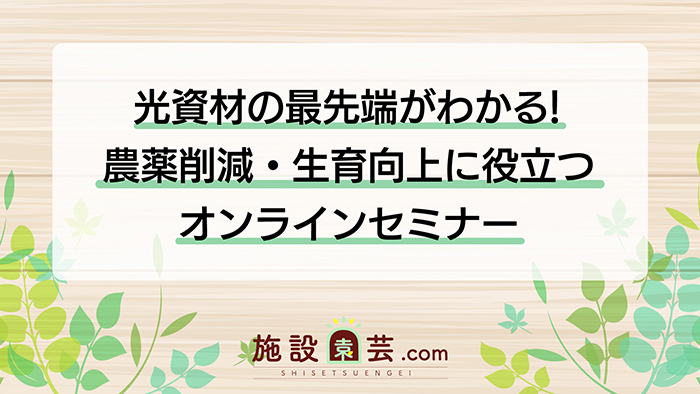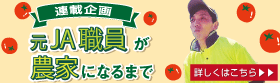こんにちは。関野です!前回は暗渠工事の重要さをご紹介しました!そして今回…本連載もいよいよ最終回です。正直、今までで一番過酷だった「ハウス完成→定植→初収穫」までの道のりをご紹介します。
1.ハウス完成!
朝7時から研修開始!
2ヶ月くらいでハウスが建ちました。5連棟で、間口は10m、長さ50mのハウスを建てました。25aあります。一つだけ短い棟があり、その空いたスペースに作業場を作りました。駐車場のスペースや仮設トイレを置くためにもこのような作りにしました。
2.ハウスの内装を鉄パイプで自作!
定植は12/11。苗が届く日が決まっていたので、この日に間に合わせるための作業が大変でした。
▲自作したハウス内誘引施設
必ずしもスケジュール通りに行くとは限りません。ハウスの工事が雨で遅れることもあり、ずっとひやひやしていました。日が落ちてからはヘッドライトをつけて作業をしていました。真冬だったけど、ハウス内でやる作業は暑く、体から湯気が出ていました。最初はヘッドライトから煙が出ていると勘違いし、爆発するのか!?と焦りました(笑)
3.Hei hei farm誕生
ハウス内の作業場はほぼ手作りです。パック詰めをする作業台はホームセンターで木の板を購入し、パソコンで作った文字を型におこし(ステンシル)、そこにスプレーを吹きかけてオリジナルのロゴマークをつけました。
▲自作した作業台
農協にいた頃からオリジナルの看板を作ったりDIYが大好きだったので、今回もホームセンターや百円ショップを巡り、使えそうなアイテムを集め、なるべくお金をかけない工夫をしました。
▲自作した作業場
姉が農作業の手伝いと事務を担当してくれています。他にもパートさんが8名。師匠のアドバイスで求人サイトを使って募集をしたのですが、新しく建てたハウスなのにこんなに集まってもらえて驚きです。自分でもSNSで募集をかけたり色々試してみたけど、求人サイトを使った応募が一番効果的でした。
初収穫のトマトを食べてみましたが、とても美味しかったです!栽培したのは千果という品種で、1粒20g以上もある2L規格です。私は伊豆の国市の果彩委員会に所属しているので、栽培した品種も出荷もみんなと一緒です。
最初は赤く色づかない状況が続き心配しましたが、委員会の仲間に相談すると天候の関係でみんな同じ状況だということが分かり、安心しました。これからもっと暖かくなるので、どんどん赤く、美味しくなっていくと思います!
▲初収穫の真っ赤なミニトマト
4.独立をしてみて
研修時代よりも、枝を折らないように、実を落とさないように…と慎重になり、パック詰めも前より注意深くなりました。責任感が違いますね。研修では言われたことをやっていればよかったのですが、今は農薬の散布日や作業のスケジュールも、全部自分で決めなければいけません。
反面、自由にもなりました。何をするにしても上司はいないですし、自分の好きにできます。農協に務めていたときは異動などありましたが、就農して、転勤もないし専門職で地元に貢献できることが本当にうれしいです。ワーキングホリデーのとき、しっかり自分と向き合い、決断をして、行動を起こしたことが今につながっていると思います。頑張り次第で給料も変わるし、やりがいがあります。休みは少ないですが、今は本当に農作業がたのしいので、気になりません。
▲オリジナルのロゴマークが入ったハウス外観
経営の勉強
経営については、「がんばる新農業人支援事業」の中で雇用や経営に関する研修で学びましたが、税金のことやレシートの仕分け方など、実践的なことはやりながら学ぶしかないです。今は農協さんに教えてもらった『WEB簿記』」を使っています。
今後の目標
まずは借金を返すことです!早く返したいですね。
ライタープロフィール
【関野 陽平】