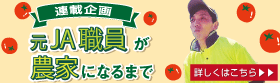新しい外国人材受入制度「育成就労制度」とは?技能実習生制度との違いについて解説
コラム
新しい外国人材受入制度「育成就労制度」とは?技能実習生制度との違いについて解説
公開日:2025.04.04

「育成就労制度」が始まるというニュースを耳にした方も多いと思います。
今までの技能実習制度が廃止になり、新たに「育成就労制度」に変わります。すでに閣議決定されているため、2027年頃には改正法が施行されると思われます。
そこでこの記事では、「技能実習制度」と「育成就労制度」の違いや注意点を解説します。
1.技能実習生制度の問題点

日本の技能実習生制度は、諸外国からの批判もいくつかありました。
例えば2022年の米国国務省の指摘は以下のように整理できます。
①制度本来の目的に反して、多くの技能実習生が技能の伝授や育成が実施されない仕事に従事している
②送出国政府と日本政府間で覚書があるにもかかわらず、労働者は過大な負担金・保証金・不明瞭な「手数料」を支払っている
③移動・通信の制限、パスポート取上げ、強制送還や家族に危害を及ぼすといった脅迫・身体的暴力・劣悪な生活環境・賃金差押え等の人権侵害がみられる
④劣悪な労働環境から逃れてきた技能実習生を、日本当局が逮捕したり、強制送還することがある
⑤特定技能ビザへの移行:在留終了時にA2相当の日本語能力試験の合格が必須
上記は、第三者である米国政府が本国まで聞こえてきたようなトラブルの事例が集約されており、日本にとっては耳の痛い内容になっています。
一方、当事者である技能実習生はどのような問題点があると感じているのでしょうか?
ここでは、1つの事例として、群馬県が2020年に実施した在留中の技能実習生224名(中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア出身)を対象としたアンケート調査結果を紹介します。
調査結果よると、「実習先で困っていることを以下から選んでください」との設問に対し、「困っていることはない」と回答した人が42.9%と最も多かったものの、次いで
■ 日本語が分からない:28.6%
■ 技能検定に合格できるか不安:16.1%
■ 給与・福利厚生:10.7%
■ 職場の人間関係:8.9%
となっています。
特に、日本語について、技能実習生の大半が「早口や方言で話されると聞き取りが難しい」「複雑な会話のやり取りが難しい」と感じています。
また、技能検定が日本語で出題されることも考えると、技能実習生の半分程度は日本語習得が課題であることが分かります。
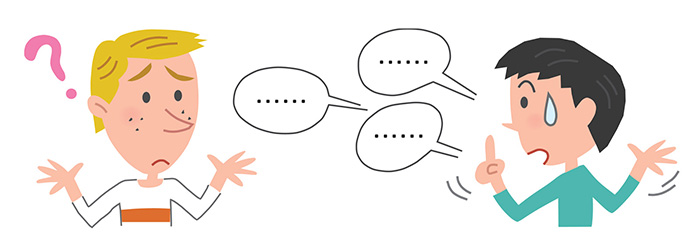
2.海外の外国人材受け入れ制度-韓国の例-

日本の隣にある韓国でも、20年ほど前から農業現場や工場での人手不足に悩んでおり、2007年から「外国人勤労者雇用許可制」により外国人材を受け入れています。
最初のうちは、劣悪な労働条件や賃金不払い等が問題になったものの、徐々に制度が改善されています。
ここでは、筆者の書いた記事や論文「日韓における外国人労働者受け入れ対策の比較分析」を参考に整理した日本の「技能実習生制度」との主な相違点を以下の表1に示しました。
※なお、日韓両国とも、労働関係法令や社会保険加入を遵守する代わりに、家族を呼び寄せて在留することは認めていないことは共通しています。
| 制度 | 技能実習 | 育成就労(2027年までに施行) | 外国人勤労者雇用許可制 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 国際貢献のため、開発途上国の外国人を受入れ業務を通じて技能を移転 | 外国人が就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり日本の産業を支える人材を確保 | 国内居住者を雇えない中小企業が政府から雇用許可書の発給を受け、合法的に非専門外国人材を雇用 |
| 受入国 | 全世界を対象とするが、ベトナム、インドネシア、フィリピン、中国、ミャンマーの6か国で90%を占める | 原則として、二国間協力覚書(MOC)を作成した国からのみ受入(特定技能でのMOC締結国は下記注のとおり) | 了解覚書(MOU)を締結した16ヵ国フィリピン、タイ、インドネシア、ベトナム、モンゴル、ウズベキスタン、カンボジア、パキスタン、中国、バングラデシュ、キルギス、ネパール、ミャンマー、スリランカ、東ティモール、ラオス |
| 受入時の試験 | 特になし | 日本語能力A1相当以上の試験の合格又はこれに相当する認定機関による日本語講習の受講 | EPS-TOPIK(雇用許可制韓国語能力試験)合格者のみ入国・就労可能。EPS-TOPIK点数が高い外国人材は希望職種に就業しやすい。 |
| 入国者数の管理 | 特になし | 生産性向上を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を設定して運用 | 国内での雇用状況を踏まえて総枠を決め、MOU締結国にも個別に交渉 |
| 年齢 | 18歳以上 | (未定) | 入国時点で18~39歳に限る |
| マッチング | 日本の監理団体+外国の送出機関を通じて実施 | 日本の監理支援機関+外国の送出機関を通じて実施 | 政府の雇用支援センター(日本のハローワークに相当)に雇い主が求人を出しても自国民が応募しない場合に外国人材をあっせん |
| 事業所ごとの受入れ人数枠 | 職員総数に応じた人数枠あり | (未定) | 施設園芸ではハウス面積が要件 4000~ 6499㎡:15人以内 6500~ 11499㎡:20人以内・・・ |
| 在留期間 | ・1号:1年以内 ・2号:2年以内 ・3号:2年以内 |
原則3年間(満了後、「特定技能」への移行に必要な能力試験で不合格になった場合は最長1年の延長が可能) | 原則3年間(+雇い主の希望により1年10か月以内で延長が可能) |
| 計画策定の要否 | 号数が変わるごとに技能実習計画の策定が不可欠 | 3年分の育成就労計画の策定が不可欠 | 特になし |
| 転籍・転職 | 原則不可 | 一定の要件の下、本人の意向による転籍可能(同一業務区分+一定の技能や日本語能力等) | 正常な労働関係の持続が困難である場合、最大4回まで可能 |
※注:日本の「特定技能」でMOCを締結した国は以下のとおりです。
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギス、タジキスタン
表1からは、
①韓国で外国人材が就労するためには、年齢や語学力等の能力が要求される
②韓国では日本の「団体監理」という概念がなく、政府が監理団体の役目を担う(手数料問題が起きにくい)
③韓国の外国人材は、政府機関が認めれば一定の範囲内で転職の自由がある
ことが分かります。
3.技能実習生制度を改善した「育成就労制度」とは?

以上述べてきた課題を踏まえ、現在の「技能実習法」を大幅に改正する形で、2024年6月に「育成就労法」が公布されました。
ただし、「育成就労法」が実際に施行されるのは、「公布日から3年以内」なので、施行されるのは2027年頃、法律を実際に動かしていく指針は2025~2026年に策定されます。
現状では詳細未定である部分も多々ありますが、先の表1をもとに育成就労制度の改善点をまとめると、以下のように整理できます。
・受入国
悪質な外国送り出し機関を排除するため、二国間協力覚書を作成した国からのみ受け入れ
・日本語能力
ある程度の日本語ができる人材だけを受け入れ
・計画策定
技能実習より策定の回数が減少(3年間で2回→1回)
・転籍
同一の業務区分であれば、経験や日本語能力等により一定の条件下で転籍を認める
一方、技能実習生制度と大きな差がない点をまとめると以下のとおりです。
・マッチング
技能実習生制度の「監理団体」が「監理支援機関」に変わりますが、大きな流れは変わらないと考えられます。
・点数制度
受入機関や監理団体が何らかのトラブルを起こした場合、評価点が減少することにより、受入の停止や次年度の受入人数枠の減少が起きることも従来どおりです。
現状は指針が定まっていない事項は受入年齢と人数枠です。受入機関ごとの人数枠を設けることは決まっていますが、具体的な基準までは定められていません。
4.外国人材を初めて受け入れる場合は2026年までに

育成就労制度は実施方針がまだ定まっていない制度です。一方、育成就労制度のスタート時点で既に来日している技能実習生は、引き続き「技能実習」ビザで在留できるとされています。
よって、外国人材の受け入れを望んでいる場合、第一陣は制度的に安定している技能実習生で受け入れていくのが無難だと思われます。
今後の課題
優秀な外国人材を定着させる工夫が必要になるでしょう。
受入機関から見た「特定技能」制度の課題として、外国人材の転職が可能であり、人材が定着しにくいことが指摘されています。また、育成就労制度も、同一職種であれば、日本語能力など一定の条件下で転籍が認められており、転籍できる地域の範囲も定められていません。
すなわち、育成就労制度では、技能や日本語能力が高い(≒仕事の習熟が早く、日本に順応している)外国人材が、給与や労働条件がより恵まれている受入機関に転籍する可能性が高くなることが予想されます。
よって、外国人材の流出を防ぐための「働き方改革」の必要性はより高まることが考えられます。
また、技能実習生の場合、日本語が分からないことを悩みに上げる人がもっとも多く、日本語能力が高いほど仕事での満足度も高いことが分かっています。
加えて、受け入れ機関が育成就労外国人に日本語能力試験を受けさせることが義務化され、外国人側も日本語能力の習得が義務化される運用になります。
これらのことから、外国人材をつなぎとめる方策の一つとして、日本語の学習ができる機会を増やすことが必要になってくると考えられます。
以上本記事では、技能実習制度の問題点を簡単に触れたのちに、韓国を例に外国人材の受け入れ方法を説明し、「技能実習制度」と「育成就労制度」の違いや注意点を整理してみました。
外国人材の受け入れは、今後日本社会全体の人材不足が一層進むことを考えると、規模拡大時に検討すべき制度になっていると思います。その中でも、育成就労制度は、まだ施行されていないため、これから具体的な内容が明らかになる部分も多い制度です。
全容が分かった際には改めて「育成就労制度」に関する詳しい解説が出来ればと思います。
- ▼関連記事
▼参考
〇法務省,技能実習制度に対する国際的な指摘について,外務省資料
https://www.moj.go.jp/isa/content/001385807.pdf
〇群馬県, 外国人留学生・技能実習生等実態調査結果
https://www.pref.gunma.jp/site/gaikokujinzai/3879.html
〇シン・韓国農業論,【目的から違う?】韓国と日本の外国人材受け入れの特徴が分かる5選【業種・国別の状況は?】
https://sinkankokunogyo.blog/
〇亜細亜大学, アジア研究所紀要 第29号~最新号
https://www.asia-u.ac.jp/research/asian-institute/annals/
〇入出国在留管理庁,育成就労制度・特定技能制度Q&A
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
〇入出国在留管理庁,特定技能に関する二国間の協力覚書
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
〇厚生労働省,育成就労制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf
〇農林中金総合研究所,農業分野における “育成就労制度”の注目点,株式会社農林中金総合研究所 主事研究員石田 一喜
https://www.nochuri.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/otr20240724-01.pdf
〇国土交通省,特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001761559.pdf
〇特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針について,令和7年3月11日閣議決定
https://www.moj.go.jp/isa/content/001434808.pdf