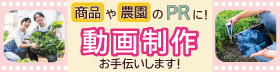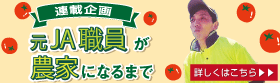キノコ菌床で堆肥作り!作り方や材料は?農家の事例紹介
コラム
キノコ菌床で堆肥作り!作り方や材料は?農家の事例紹介
公開日:2019.12.10

良い作物は良い土作りから!作物が育つ良い土壌を育むため、農家のみなさんはそれぞれ色々な工夫を凝らした堆肥作りをされていると思います。今回は堆肥作り中でも、キノコ菌床に注目し、その特徴や堆肥作りの事例についてご紹介します。
1.肥料と堆肥の違い

肥料は、作物が成長するために必要な養分を供給するために使用するもので、化学肥料と有機質肥料に2つに分けられます。
化学的手法で作られた肥料で、効果がすぐ出やすいのが特長です。
植物由来もしくは動物由来の原料から作られた肥料です。土壌内でゆっくりと分解されるため、効果が長続きします。
一方堆肥は、有機質肥料の1種で藁やもみ殻、牛糞や鶏糞などの有機物を堆積(または攪拌)したあと、腐熟させたものです。品質が一定ではなく、含有する成分量も保証されていないもののことで、土壌改良効果も持ち合わせています。なお、腐葉土は落ち葉が堆積し腐熟させたものを指します。
発酵させて腐らせること。
- ▼関連記事
2.キノコ菌床を活用しよう!

キノコの栽培方法は「原木栽培」と「菌床栽培」の2種類ありますが、菌床栽培のあとに廃棄されるものが「キノコ菌床(廃菌床)」です。 キノコ菌床は、オガクズなどの木質基材に栄養源となる米ぬかなどを混ぜて植菌したものが使われます。有機物を材料としていることから堆肥化を行うことで有機資材として使用することができます。
特徴としては、C/N比が50から100程あり、水分量がある程度保持されています。
●保存状態にもよりますが、廃棄直後であれば水分量が60%程度あるので、堆肥の材料として混ぜたあとに水分調整がしやすいです。
●オガクズや米ぬかなど、原料が細かいため、堆肥の材料として均一に混ぜやすく、また散布機などで散布できます。
●キノコ菌床はもともと廃棄されるものなので、1tあたり数百円と格安で販売しているところもあります。また、工場の規模にもよりますがまとまった量を入手しやすいです。
●キノコ菌床にはリン酸(P)やカリ(K)、窒素(N)が樹皮などの木質系資材に比べ2~4倍含まれています。また、易分解性炭素源も多く含むため、微生物が活動しやすくなり、発酵の促進に役立ちます。
💡注意
キノコ菌床が、完熟堆肥になるまでの目安は4~6ヶ月です。長期間かかるため、自作する場合は計画的に準備しましょう。
3.キノコ菌床を使った堆肥の作り方!事例紹介

ここからはキノコ菌床を使って堆肥作りをした事例をご紹介します。
● 材料
廃菌床(広葉樹チップ、米ぬか、ふすま)、鶏糞
● 作り方
廃菌床と鶏糞を混ぜ合わせ、水分を調整します。菌床と鶏糞の割合は16:1~8:1程度です。鶏糞を多めにすると肥料としての効果が高まります。
雨風に当たらないよう堆肥舎で、コンクリート床の上や堆肥枠の中で発酵を行います。温度が下がったら切り返しや水分補給を行い、4カ月程度で発酵が終了します。
● 材料
廃菌床(杉オガクズ、米ぬか、脱脂大豆など)
● 作り方
シメジ栽培の廃菌床のみを使い発酵させています。水分量65%程度で堆積発酵させ、温度が下がったら切り返し、70日程度で高温発酵が終了します。施用後は窒素の取り込みがゆっくりなので、遅効性の肥料成分が期待できます。
● 材料
廃菌床(コーンコブなど)、もみ殻、稲わら
● 作り方
畑の横にもみ殻、稲わら、廃菌床を運び込み、その場に野積みしていきます。2週に1回程度切り返しを行い、1年程度発酵させてから散布機で畑に散布します。
●メリット
モミガラ廃菌床は水はけが良いため、雨の多い年にも水たまりがほとんどできません。とくに、レタスの場合は水が抜けないと病気や生育不良になる恐れがあるため、水はけの良さは大きなメリットとなっています。
● 材料
廃菌床(シメジ・えのき混合)、微生物資材
● 作り方
廃菌床70tに対して微生物資材1.2t投入したものを混ぜ合わせ、適宜切り返しを行い、4カ月後には完熟堆肥化されます。
埼玉県のミニトマト農家さんの声
私の周りはみんなキノコ菌床を使った堆肥を作っており、業者からまとめて仕入れています。 配送の距離があるのですが、それでも3トンで4万円ほどです。 稲わら(稲の堆肥)は1年ほどでダメになってしまいますが、キノコ菌床は木くずが残るため長持ちします。 泥がやわらかいので、根の張りや酸素の吸収が良くなりますよ。水はけも良いですね。 キノコ菌床を使う場合は菌体が違うので、使用前に一度熱を通したほうがいいですよ。

以上、菌床を使った堆肥作りについてご紹介しました。キノコ菌床は産業廃棄物になるため、ゴミとして処分するにも費用がかかります。しかし、使い方次第で有用な地域資源になります。 皆さんも、身近な地域資源を使って良い土づくりをしてみてください。
※2019.12.10 公開の記事をリニューアル更新しました。
- ▼関連記事
▼参考文献
〇シイタケ廃菌床の施肥化技術, 徳島県森林林業研究所
http://www.pref.tokushima.jp/_files/00212304/shitakehaikinnsyou.pdf
〇施肥後の土壌酸性化を大きく低減するきのこ廃菌床堆肥製造技術の研究開発, (財)名古屋産業科学研究所
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/portal/seika/2009/21h-186-19-4.pdf
〇食用キノコ廃培地の堆肥化について, 吉田兼之
https://www.hro.or.jp/list/forest/research/fpri/rsdayo/12461002001.pdf
〇菌床堆肥の野菜畑への施用効果, 荒木卓久・道上伸宏
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/gijutsu/nougyo_tech/kenyui/kenkyu_seika/tayori/104-4.data/104-4.pdf
〇肥料取締法について,農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/kana_26.pdf
▼参考サイト
〇シメジ廃菌床の早期堆肥化とその利用, 高知県農業技術センター
https://www.naro.affrc.go.jp/org/warc/research_results/skk_seika/h06/94022.htm
〇モミガラを急速発酵させる廃菌床の力,現代農業
http://www.ruralnet.or.jp/gn/201710/momigara.htm

ライタープロフィール
【内村耕起】
宮崎県の牛農家生まれ。大学院で植物工場での廃棄物利用に関する研究に従事したのち、全国の農家を訪ね歩いてファームステイ。岩手県の自然栽培農家で2年間の農業研修を経て、現在は宮崎県の山間部の村で自給的農業を営む傍ら、ウェブライターなどもしています。